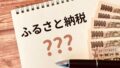この記事では、保険金を受け取った際に確定申告が必要かどうかを、具体例を交えてわかりやすく解説します。生命保険や死亡保険金など、さまざまな保険金の受け取り時にかかる相続税、所得税、贈与税について詳しく紹介し、その計算方法も取り上げています。確定申告の手続きが必要な方に役立つ情報が満載です。保険金の受け取り方次第で異なる税金について知りたい方は、ぜひ最後までお読みください。
生命保険会社から受け取るお金の種類
生命保険会社から受け取るお金には「給付金」と「保険金」の2種類があります。それぞれの特徴について詳しく見ていきましょう。
給付金
給付金とは、病気やケガの治療費、入院費、手術費などが発生した際に、生命保険会社から支給されるお金です。具体的には、入院や手術後に申請することで受け取ることができます。給付金の金額は、契約内容や保険商品によって異なり、治療費や生活費の補填に使われます。
給付金には、以下のような種類があります。
- 入院給付金
- 手術給付金
- 通院給付金
- 在宅医療給付金
- 先進医療給付金
- 女性疾病入院給付金
治療が長引いた場合でも、保険契約を継続している限り、給付金を何度でも受け取ることが可能です。
保険金
保険金とは、被保険者が亡くなった際や、保険の契約満了時に支払われるお金です。一度受け取ると、その時点で保険契約は終了します。保険金の金額も契約内容や保険の種類によって異なり、遺族の生活保障や住宅ローンの支払いなど、様々な用途に使われます。
具体的な保険金の例は以下の通りです。
- 死亡保険金
- 高度障害保険金
- 特定疾病保険金
給付金は保険契約が続く限り支給されますが、保険金は受け取ると契約が終了する点を覚えておきましょう。
保険金にかかる税金
生命保険会社から受け取る保険金には、主に以下の3つの税金がかかります。
- 相続税
- 所得税
- 贈与税
それぞれの税金について、具体的な適用条件と特徴を解説していきます。
相続税
保険の契約者と被保険者が同じ場合で、保険金の受取人が異なる場合に相続税が課されます。被保険者が亡くなった後に支払われる保険金以外にも、現金や預貯金、不動産などに相続税がかかるケースがあります。
例えば、夫が契約者・被保険者で、妻が受取人の場合、この保険金に相続税が課されます。同様に、契約者と被保険者が同じで、受取人が子どもの場合も相続税が適用されます。
所得税
契約者と保険金の受取人が同一で、被保険者が別の人である場合には、保険金に所得税がかかります。この場合、受取金額が一定額を超えると、所得税および復興特別所得税の確定申告が必要です。
具体例として、夫が契約者で妻を被保険者に設定し、保険金の受取人も夫である場合には、受け取った保険金に対して所得税が発生します。また、年金形式で受け取る場合には雑所得として、保険金を一括で受け取る場合には一時所得として課税されます。
贈与税
契約者、被保険者、受取人がすべて異なる場合には、保険金に贈与税が課されます。たとえば、夫が契約者、妻が被保険者、子どもが受取人という場合、この保険金に対して贈与税が適用されます。また、学資保険や年金保険などでも、受取人が契約者と異なる場合には贈与税の対象となります。
保険金にかかる税金の計算方法
ここでは、相続税、所得税、贈与税の具体的な計算方法について詳しく見ていきます。
相続税の計算方法
相続税は「受け取った保険金額-非課税限度額」で計算します。非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」で求められます。
たとえば、法定相続人が3人で、保険金が2000万円の場合、「2000万円-500万円×3=500万円」が相続財産となります。この500万円に対して相続税がかかることになります。相続税の申告と納税は、被保険者が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。
所得税の計算方法
所得税は、保険金が一時所得か雑所得かで計算方法が異なります。
一時所得の場合
「受け取った保険金-支払った保険料-特別控除50万円×1/2」で計算します。たとえば、2000万円の保険金を一括で受け取り、支払った保険料が450万円の場合、
「2000万円-450万円-50万円×1/2=750万円」となり、この750万円が一時所得として課税対象になります。
参考:所得税の税率
雑所得の場合
保険金を年金形式で受け取る場合は雑所得となり、
「1年間に受け取る保険金-対応する支払い保険料」で計算されます。
支払い保険料は、「受け取った保険金額×支払った保険料の総額÷保険金の総額」で算出されます。
例)1年間に100万円受け取れる保険で、受け取り期間は10年。年額24万円の保険料を30年間支払った場合で計算
支払った保険料の総額は、24万円×30年で720万円。保険金の総支給見込額は、100万円×10年で1,000万円です。
対応する支払い保険料の金額は、100万円×720万円÷1000万円=72万円となります。
1年間に受け取る保険金100万円から72万円を差し引いた28万円から各種控除を差し引き、所得税率をかけて支払う所得税を計算します。
所得税は3月15日までに確定申告をし、申告書の提出と納税を行う必要があります。
贈与税の計算方法
贈与税は「受け取った保険金額-基礎控除110万円」で計算します。
たとえば、1000万円の保険金を受け取った場合、
「1000万円-110万円=890万円」が贈与税の課税対象になります。
贈与税の申告期限は、保険金を受け取った翌年の2月1日から3月15日までです。
保険金の確定申告は必要?
保険金に対する確定申告が必要かどうかは、保険の種類や金額によって異なります。
医療保険関連は確定申告不要
医療保険で受け取る給付金は、基本的に非課税のため、確定申告は不要です。
ただし、医療費控除を申請する場合は、確定申告が必要になります。
該当する給付金の例としては、以下が挙げられます。
- 入院給付金
- 手術給付金
- 放射線治療給付金
- 通院給付金
- 疾病(災害)療養給付金
- 特定損傷給付金
- がん診断給付金
- 特定疾病(三大疾病)保険金
- 先進医療給付金
- 障害保険金(給付金)
- 高度障害保険金(給付金)
- リビング・ニーズ特約保険金
生命保険の死亡保険金や満期保険金・解約返戻金は確定申告が必要
生命保険で死亡保険金や満期保険金、解約返戻金を受け取った場合、所得税や贈与税がかかるため、確定申告が必要です。
特に、満期保険金や解約返戻金は一時所得として課税されるため、20万円を超える所得が発生した場合には、確定申告が必須です。
受け取った保険金額が非課税限度額を超えた場合も、相続税の確定申告が求められます。
保険金の確定申告が必要となるケース
- 年間20万円以上の一時所得がある場合
- 所得税の基礎控除額を超える保険金を受け取った場合
- 会社員であっても、副収入やその他所得が合計20万円を超える場合
これらのケースでは、税務署への確定申告が必要になります。
給与の年間収入額が2,000万円以上の会社員も、保険金とあわせて確定申告を行ってください。
まとめ:保険金の確定申告は保険の種類や条件により異なる
保険金を受け取る際の確定申告の必要性は、契約内容や保険の種類、受け取る金額により大きく異なります。生命保険での給付金や保険金の取り扱いに対して、正しい申告を行うことが、将来の税務トラブルを防ぐ鍵となります。契約時に確認しておき、受け取る際にも適切に手続きを進めることが大切です。もし疑問点がある場合は、税理士や保険の専門家に相談することをおすすめします。
理想の税理士を探すなら「税理士紹介をぶっ壊す」
- 税理士紹介サイトに騙されたくない
- 顧問料に応じた税務サービスを受けたい
- 税理士の人となりを自分の目で見て選びたい
「税理士紹介をぶっ壊す」では、このようなご要望をお持ちの方のための税理士検索サービスを提供しております。
税理士紹介サイトの「闇」を知らずに税理士を探される方もいるでしょう。
当サービスでは、本当の意味で、あなたにとって理想の税理士に出会うことが可能です。無料で今すぐ検索できるので、お気軽にご利用ください。