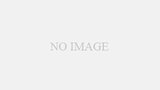ソーシャルレンディングを利用する際に注意が必要なのが確定申告です。正しく申告しないと脱税のリスクが伴います。本記事では、ソーシャルレンディングの利用によって確定申告が必要となるケースや具体的な手続き方法を詳細に解説します。
ソーシャルレンディングにおける確定申告の必要性
ソーシャルレンディングとは
ソーシャルレンディングは、資金を運用したい個人と資金を必要とする事業者をオンラインプラットフォームでつなぐ新しい形の投資サービスです。近年、特にベンチャー企業やスタートアップにとって資金調達の手段として人気が高まっています。
投資家はソーシャルレンディングのプラットフォームを通じて匿名組合契約を締結し、自身が出資した資金は選定された事業者によって運用されます。このプロセスは少額から始められ、さまざまなプロジェクトに分散して投資できる柔軟性が魅力です。プラットフォームは多くの投資家から集めた資金を合算し、資金ニーズを持つ事業者へと融資を行う重要な役割を果たします。
確定申告が必要な場合
ソーシャルレンディングによって利益を得た場合、確定申告が必要になるケースを以下に示します。
- 会社員の場合
ソーシャルレンディングの利益は一般に源泉徴収されるため、多くの会社員は確定申告が不要なことが多いです。たとえば、給与所得が年間2000万円以下で、雑所得が20万円以内であれば、確定申告は原則必要ありません。しかし、給与所得が2000万円を超える場合や雑所得が20万円を超える場合には、確定申告が求められます。加えて、給与を二つ以上の職場から得ている場合や、その他の所得が20万円以上ある場合にも確定申告が必要です。なお、ソーシャルレンディングはマイナンバーと連携しているため、脱税が発覚しやすい仕組みになっています。確定申告が必要な場合は、必ず正直に申告を行いましょう。
- 個人事業主やフリーランスの場合
個人事業主やフリーランスは、会社員とは異なり、通常、確定申告が必要です。収入が全くない場合を除き、所得がある場合には必ず申告を行う必要があります。特に、事業運営による利益や雑所得が生じる場合は、正確に申告を行いましょう。
- 専業主婦の場合
専業主婦がパートタイムで収入を得ている場合、年末調整が行われている限り、確定申告は不要とされています。しかし、専業主婦の所得が合計で38万円を超える場合、確定申告が求められます。たとえば、ソーシャルレンディングの収入やパート収入を合算し、38万円を超えた場合は、確定申告を忘れずに行うべきです。また、アルバイトやパートの場合、必要以上に源泉徴収が行われていることもあります。年末調整が行われない職場に勤務している場合は、確定申告を行うことで還付金が受けられる可能性があるため、必ず申告を検討しましょう。
確定申告が不要な4つのケース
ソーシャルレンディングを利用している場合でも、確定申告が不要なケースがあります。以下の条件に該当する場合は、申告が不要となります。
- 一箇所からの給与受取:給与が一箇所からの支払で、年収が2000万円以下かつソーシャルレンディングとその他の所得の合計が20万円以下の場合。
- 二箇所からの給与受取:給与が二箇所から支払われていて、年収が2000万円以下、かつ年末調整が行われていない給与の収入金額とソーシャルレンディングおよびその他の所得の合計が20万円以下の場合。
- 公的年金の受取:公的年金の収入が400万円以下で、それ以外の給与やソーシャルレンディングおよびその他の所得の合計が20万円以下の場合。
- 控除額以下の場合:給与や公的年金、ソーシャルレンディングなどのその他の所得の額が基礎控除や社会保険料控除などの控除額合計以下の場合。
ソーシャルレンディングによって雑所得が0円以下になる場合など、条件を満たすと確定申告が不要となることがあります。ただし、還付金の受け取りを希望する場合は、自主的に申告を行うことをお勧めします。
近年、ソーシャルレンディング市場は急速に拡大しており、各プラットフォームが提供する情報も多様化しています。最新の税制変更や投資法について、定期的に情報をチェックすることが重要です。また、マイナンバー制度の影響で、今後の税務調査が厳しくなる可能性もありますので、慎重に取り扱う必要があります。
確定申告が不要でも住民税の申告は必要
確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は必ず行う必要があります。このセクションでは、住民税の申告を怠った場合のリスクや、正しい申告方法について詳しく解説します。
住民税の申告をしなかった場合のリスク
ソーシャルレンディングで得た雑所得が年間20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は税務署または地方自治体に対して行わなければなりません。特に個人事業主の場合、確定申告だけでなく住民税の申告をしないと、健康保険料などの費用も確定しないため注意が必要です。
住民税には「所得割」と「均等割」が存在し、それぞれの課税条件が異なるため、実際に納めるべき金額は市町村ごとに異なります。さらに、各市町村が設けている控除制度や税率もさまざまであり、具体的な納税額は市町村の公式ホームページで確認することをおすすめします。
住民税の申告をしなかった場合、延滞金が発生する可能性があります。加えて、自治体から注目され、次年度からの確認が厳しくなることも考えられます。さらに、各種市民サービスの利用が制限されることもあります。ソーシャルレンディングで得た利益を無駄遣いして納税できない場合でも、必ず申告を行い、納税は延期してもらう手続きをしましょう。確定申告が不要だからと気軽に考えず、しっかりと市町村の情報を確認することが大切です。
住民税の申告方法
ソーシャルレンディングで得た雑所得が年間20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は税務署または地方自治体に対して行わなければなりません。特に個人事業主の場合、確定申告だけでなく住民税の申告をしないと、健康保険料などの費用も確定しないため注意が必要です。
住民税には「所得割」と「均等割」が存在し、それぞれの課税条件が異なるため、実際に納めるべき金額は市町村ごとに異なります。さらに、各市町村が設けている控除制度や税率もさまざまであり、具体的な納税額は市町村の公式ホームページで確認することをおすすめします。
住民税の申告をしなかった場合、延滞金が発生する可能性があります。加えて、自治体から注目され、次年度からの確認が厳しくなることも考えられます。さらに、各種市民サービスの利用が制限されることもあります。ソーシャルレンディングで得た利益を無駄遣いして納税できない場合でも、必ず申告を行い、納税は延期してもらう手続きをしましょう。確定申告が不要だからと気軽に考えず、しっかりと市町村の情報を確認することが大切です。
ソーシャルレンディングで確定申告をしたほうが良い場合
ソーシャルレンディングを利用している方が確定申告を行ったほうが良い場合について解説します。
給与所得と分配金の合計が195万円以下の場合
確定申告をすることで還付金を受け取れる可能性があります。ソーシャルレンディングで得られる配当金は既に20.42%の源泉徴収が行われていますが、この源泉徴収はあくまで予想される所得税を事前に差し引いたものであり、実際の所得税額とは異なる場合があります。
例えば、本業で赤字を計上した場合、実際の所得税率が20.4%よりも低くなることがあります。また、所得が低い場合、所得税額自体も少なくなるため、この際も還付申告を行うことで還付される可能性があります。正確な税額を把握するためにも、確定申告を行い、しっかりと計算してみることが重要です。
確定申告は面倒に感じるかもしれませんが、しっかりと計算することで還付を受けられる場合があります。また、実際に納税が必要なことが明らかになることもあります。国税庁の公式ホームページでは計算が簡単にできるので、ぜひ活用してください。もちろん、税理士に相談することも効果的です。
ソーシャルレンディングの利益に対する課税の仕組み
ここでは、ソーシャルレンディングの利益に対する課税の仕組みを分かりやすく解説します。
ソーシャルレンディングの分配金は雑所得
ソーシャルレンディングで得た配当金は雑所得として扱われます。給与所得や配当所得として計上しがちな誤解があるため、注意が必要です。雑所得を計算する際は、配当金からソーシャルレンディングにかかった経費を引きます。通信費、セミナー代、交通費などは経費として計上可能ですが、経費として認められないものも存在するため、事前に確認しておくことが重要です。
また、ソーシャルレンディングにおいては、さまざまなキャンペーンで得られる金銭もありますが、これらは一時所得として扱われます。一時所得の場合、50万円未満であれば全額免除され、それを超える場合は50万円が免除となる特例があります。
ソーシャルレンディングは総合課税
ソーシャルレンディングは総合課税に該当します。つまり、給与所得などと合算して、その合計額に対して課税されることになります。この点が、他の投資方法との大きな違いです。例えば、FXなどでは分離課税が一般的です。総合課税は、納税の際に有利になることもあるため、ソーシャルレンディングの一つの利点と考えられます。
給与所得が多ければ多いほど、納税額は累進的に増加します。逆に所得が少ない場合には、納税が不要になるだけでなく、確定申告を行うことで還付を受けられるケースもあります。このため、確定申告を行うことが推奨されます。
ソーシャルレンディングの分配金は源泉徴収されている
ソーシャルレンディングを通じて得られる配当金や分配金は、既に源泉徴収されています。つまり、業者が配当金から想定される所得税分を引き、その残りを利用者に渡しています。このため、納税が代行される利点がある一方で、実際には過剰な税金を支払っている可能性があります。この場合には、確定申告を行い還付申告をする必要があります。
源泉徴収される税率は20.42%であり、内訳は所得税が20%、復興特別所得税が0.42%です。復興特別所得税は2037年までの期間、継続される予定です。このように、配当金にかかる税金は高めに設定されているため、今後の節税対策を検討することが求められます。
なお、住民税に関しては、ソーシャルレンディングからの分配金に対してはその場での源泉徴収が行われないため、確定申告を行わない場合は、住民税の申告を別途行う必要があります。
ソーシャルレンディングの確定申告の手続き
ここでは、ソーシャルレンディングを利用して得た収益に対する確定申告の手順を詳しく解説します。確定申告の方法を理解することで、適正に税務を行うことができ、法的なリスクを回避することが可能になります。
必要書類の確認
確定申告を行う際には、主に確定申告書の第一表と第二表が必要です。これらの書類を正確に記入するためには、ソーシャルレンディングから受け取った分配金額や源泉徴収税額を示す書類、例えば年間取引報告書が必要になります。ただし、これらは提出書類ではありませんが、記入の基礎となります。
また、確定申告を行う際にはマイナンバーの提示が求められます。提出方法によっては、本人確認書類のコピーが必要になることもあるため、事前に準備しておくと良いでしょう。
確定申告書の書き方
ソーシャルレンディングから得た分配金の確定申告の手順について、簡潔に説明します。まずは、ソーシャルレンディングからの年間取引報告書を手に入れ、その内容に基づいて確定申告書第二表の「所得の内訳」欄に必要情報を記入します。分配金は「雑所得」として扱われるため、「所得の種類」には「雑所得」と記入し、「種目」には「分配金」と書きます。
支払者の名前や住所には、ソーシャルレンディング事業者の情報を入力し、収入金額欄には受け取った分配金の額を、源泉徴収税額欄には源泉徴収された税金の額を記入します。もし経費が発生している場合は、収入から経費を差し引いた額を所得金額に記入する必要があります。ソーシャルレンディングの分配金に関連する経費が発生していない場合でも、他の雑所得があれば、それらを合算して計算します。
最後に、源泉徴収された税金額を確定申告書の「税金の計算」欄に記入します。これにより、所得税の計算時に源泉徴収された税額が正しく考慮されます。
確定申告書等作成コーナーでの申告フロー
オンラインで確定申告書を作成する際の大まかな手順を説明します。まず、「確定申告書等作成コーナー」のウェブサイトにアクセスし、「作成開始」をクリックします。次に、提出方法を選択する画面が表示されるので、希望する提出方法を選択します。電子申告を希望する場合は、マイナンバーカードを利用し、スマートフォンまたはICカードリーダーを使ったe-Taxのオプションを選びます。マイナンバーカードがない場合は、IDとパスワードを使ったe-Taxを選択します。
紙での提出を希望する場合は、書類を印刷して提出するオプションを選びます。次に、所得税の申告を選択し、「作成開始」ボタンをクリックします。申告者の生年月日を入力し、ソーシャルレンディングからの分配金を含む所得についての質問に答えます。この段階で、ソーシャルレンディングの収入は雑所得に該当するため、「はい」と回答します。
その後、具体的な入力画面に移行します。ソーシャルレンディングの分配金を雑所得の欄に記入し、詳細を入力します。最終的には、収入、所得、源泉徴収税額など、必要な情報を正確に入力し、所得控除やその他の必要な情報を追加することで、オンラインでの確定申告書の作成と提出が完了します。
ソーシャルレンディングを活用した節税方法
経費を計上する
ソーシャルレンディングを行う際には、経費を計上することで節税が可能です。具体的には以下のような経費が考えられます:
- 振込手数料
- セミナーの参加費や交通費
- ソーシャルレンディング関連の書籍代
- インターネットの利用料
経費として計上できる項目は多岐にわたりますが、注意が必要です。たとえば、税務署からお尋ねが来る可能性があるため、計上内容には十分な根拠を持たせることが大切です。電気代や家賃を一部計上することも可能ですが、濫用すると税務調査のリスクが高まるため注意しましょう。
家族の収入が低い方の名義で投資を行う
家族の中で収入が低い方の名義でソーシャルレンディングに投資を行うことも一つの節税手法です。例えば、妻や子供に投資をしてもらうことで、家計全体の課税所得を抑えることが可能です。例えば、ソーシャルレンディングに100万円を投資して年間30万円の利益が出たと仮定します。この場合、夫が50万円、妻が50万円分をそれぞれ投資すれば、夫も妻も年間15万円の所得を抑えることができます。この方法を使うことで、夫婦それぞれが所得額を抑えられ、確定申告も不要になります。ただし、実際の収益が予想を上回った場合には、適切に申告する必要があります。この分散投資の方法は、家族が多ければ多いほど活用しやすくなります。
法人を設立する
ソーシャルレンディングからの収入が安定して得られるようになったら、法人化を検討するのも良いでしょう。法人化することで、法人税が適用され、さまざまな経費を計上できるようになります。個人事業主であれば、法人化することによって赤字の繰越が容易になり、税務上の優遇措置を受けることができます。法人化によるメリットは、税率の軽減だけではなく、経営の柔軟性や資金調達のしやすさなど、多岐にわたります。
ふるさと納税を利用する
ソーシャルレンディングの投資案件によっては、元手が数倍に増えることも期待できますが、同時に税金負担も大きくなります。特に、ソーシャルレンディングでは所得税が2割も引かれるため、負担感が強まります。そんな中で、ふるさと納税を利用することが一つの節税策となります。ふるさと納税を活用することで、特産品を受け取りながら実質的な税負担を軽減することができます。
ただし、ふるさと納税には上限が設定されているため、計画的に行うことが重要です。
ソーシャルレンディングでの節税における注意点
ここではソーシャルレンディングで節税を行う際に注意すべき点を2つ紹介します。
所得の損益通算ができない
ソーシャルレンディングの一つの注意点は、損益通算ができないことです。つまり、個人事業主として本業で赤字が出ても、それをソーシャルレンディングの所得と合算して節税することができません。たとえば、事業所得が200万円、ソーシャルレンディングからの所得も200万円の場合、損益通算ができないため、納税が必要となります。
総合課税の場合の繰越控除ができない
ソーシャルレンディングのもう一つの注意点は、損失が出た場合に繰越控除ができないことです。つまり、損失を抱えた場合でも、その損失を翌年以降に繰り越して控除を受けることはできません。繰越控除を受けるためには、法人化など別の方法を検討する必要があります。ソーシャルレンディングはリターンが大きい分、損失が出た際には大きな痛手となることもあるため、事前にリスクを理解しておくことが重要です。
ソーシャルレンディングの確定申告まとめ
この記事では、ソーシャルレンディングに関連する確定申告について詳細に説明しました。ソーシャルレンディングで得た利益に対しては、必ず確定申告を行うことが重要です。適切に申告をしないと、脱税として扱われるリスクがあるため、注意が必要です。
また、確定申告が必要な場合には、経費を上手に活用することや法人化を検討することで、より有利に納税を行うことができます。特に経費に関しては、多岐にわたる項目が計上できるため、できる限り活用して税負担を軽減することが望ましいです。
さらに、住民税の申告を忘れがちな方も多いため、こちらも確実に行うよう心がけましょう。税務上の盲点を減らし、安心してソーシャルレンディングを楽しむための知識を身につけておくことが大切です。
ソーシャルレンディングによる確定申告は、適切な知識と手続きが必要です。今回紹介した情報を参考に、正しい申告を行い、税務リスクを回避しましょう。
理想の税理士を探すなら「税理士紹介をぶっ壊す」
- 税理士紹介サイトに騙されたくない
- 顧問料に応じた税務サービスを受けたい
- 税理士の人となりを自分の目で見て選びたい
「税理士紹介をぶっ壊す」では、このようなご要望をお持ちの方のための税理士検索サービスを提供しております。
税理士紹介サイトの「闇」を知らずに税理士を探される方もいるでしょう。
当サービスでは、本当の意味で、あなたにとって理想の税理士に出会うことが可能です。無料で今すぐ検索できるので、お気軽にご利用ください。

理想の税理士を探すなら「税理士紹介をぶっ壊す」
- 税理士紹介サイトに騙されたくない
- 顧問料に応じた税務サービスを受けたい
- 税理士の人となりを自分の目で見て選びたい
「税理士紹介をぶっ壊す」では、このようなご要望をお持ちの方のための税理士検索サービスを提供しております。
税理士紹介サイトの「闇」を知らずに税理士を探される方もいるでしょう。
当サービスでは、本当の意味で、あなたにとって理想の税理士に出会うことが可能です。無料で今すぐ検索できるので、お気軽にご利用ください。