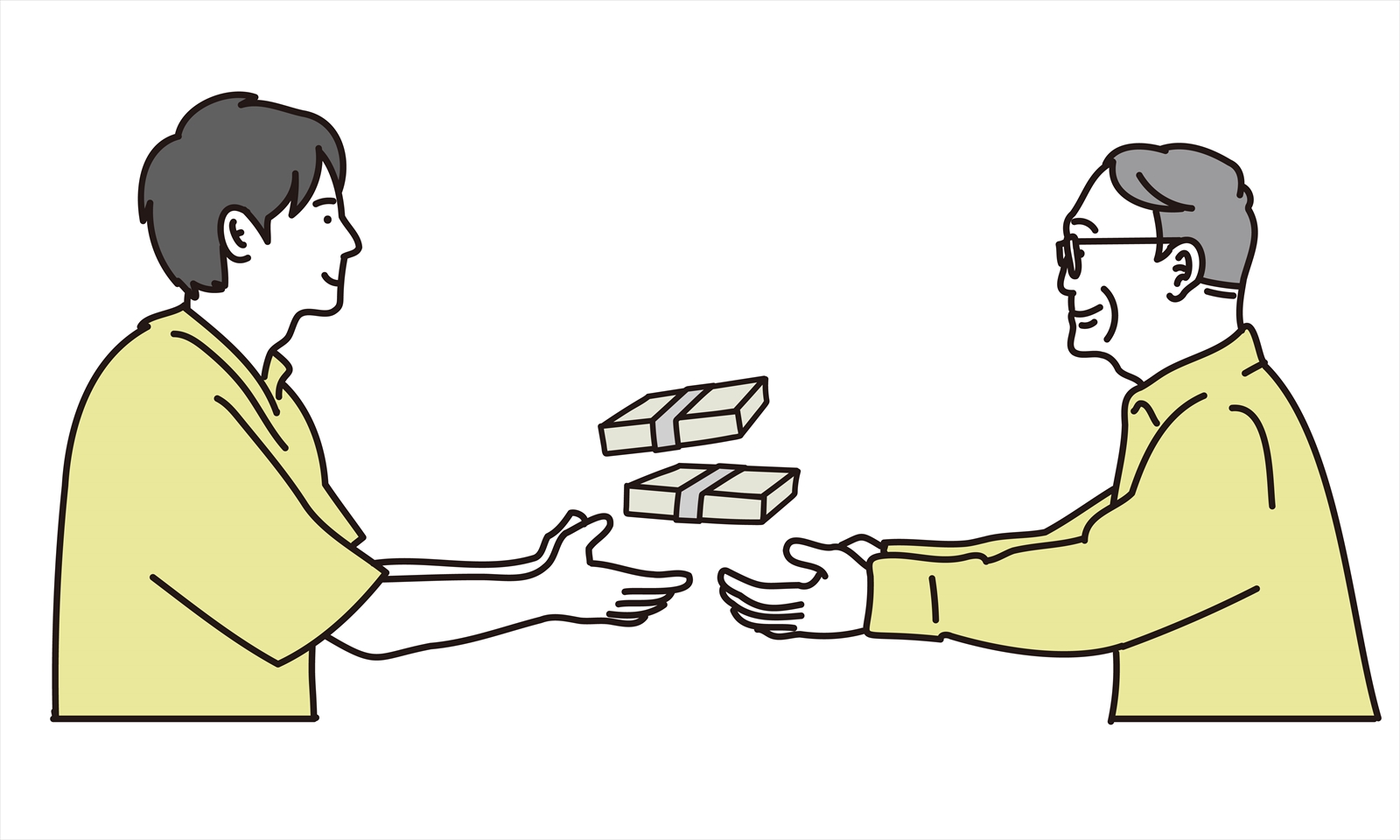贈与税は、家族間でのお金の受け渡しに関わる重要な税制です。たとえ親族や家族同士であっても、年間で一定以上の金額を贈与する場合、贈与税の申告が求められることがあります。贈与税について知らずにお金を受け渡すと、意図せず申告漏れを招く可能性がありますので、注意が必要です。
贈与税は、遺産相続時に発生する相続税と似たような税制ですが、控除額や税率において異なる点があります。生前贈与を行った場合にも贈与税が課されるため、どの金額以上の贈与が申告を必要とするのか、また控除や軽減措置についての基礎知識を持つことが重要です。贈与税が課税されるボーダーラインを把握しておくことで、賢く節税を図ることができるでしょう。
贈与税とは?
国税庁の公式サイトによると、贈与税とは“個人から財産をもらったときにかかる税金”と定義されています。具体的には、個人間で金融資産や不動産などの財産を贈与された場合、申告が必要な税金です。一方で、会社などの組織から財産を受け取った場合は、贈与税ではなく所得税が課せられます。贈与者が生存している間に行われた贈与には贈与税が適用されますが、死亡した後に財産を受け取った場合は相続税の申告が必要になります。
贈与税には、「暦年課税」と「相続時精算課税」という2つの課税方式が存在します。通常は「暦年課税」が適用されますが、特定の条件を満たす場合には「相続時精算課税」が選択できます。
贈与税の課税方式
暦年課税
「暦年課税」の基本的な仕組みとして、年間110万円までの基礎控除が設定されています。つまり、1年間に贈与された金額が110万円以下であれば、贈与税は課されず、申告の必要もありません。たとえば、同じ年に2名から合計200万円の現金を受け取った場合、控除額を超える90万円分が贈与税の課税対象となります。基本的に、110万円を超える金額が課税対象ですが、贈与者との関係によって基礎控除額や税率が異なることがあります。
相続時精算課税
「相続時精算課税」は、生前贈与を行う際に選択できる課税方法であり、1年間に1人あたり最大2,500万円の贈与が控除対象となります。この金額を超える部分には贈与税が課せられ、申告と納税が必要です。「相続時精算課税」は「暦年課税」と比較して非常に有利な制度ですが、贈与者を事前に指定しなければならず、一度選択すると「暦年課税」への変更はできません。この方法を利用するためには、税務署に届出書を提出する必要があり、控除額内であっても申告を行う必要があるため、注意が必要です。
贈与税の税率
一般税率
贈与税の税率は、基礎控除を差し引いた課税対象額に応じて10%から55%の範囲で累進課税が適用されます。この一般税率が適用されるのは、例えば夫婦、兄弟、親から未成年の子供などへ財産を贈与した場合です。
特例税率
20歳以上の受贈者が親や祖父母といった直系親族から財産を贈与された場合には、「特例税率」が適用されます。特例税率は一般税率よりも有利な条件で設定されており、特定の条件を満たせば適用されます。特例税率も一般税率同様、贈与額に応じた段階的な累進課税が適用されます。
贈与税の計算方法と実際の計算例
贈与税の計算方法について、年間贈与額が合計800万円で、一般税率と特例税率それぞれのケースをシミュレーションします。
一般贈与財産を800万円受け取った場合
最初に110万円の基礎控除を差し引き、課税対象額は690万円となります。この690万円に対して控除額は125万円で、税率は40%が適用され、納税額は276万円から控除額を引いた151万円となります。
特例贈与財産を800万円受け取った場合
同様に、110万円を差し引いた690万円が課税対象となり、税率は30%、控除額は90万円です。したがって、納税額は690万円の30%から90万円を引いた117万円となります。
一般贈与財産が200万円で特例贈与財産が600万円の場合
110万円の基礎控除を引いた690万円が課税対象です。一般贈与分は230万円、特例贈与分は460万円で、それぞれの計算を行います。一般贈与については税率15%(控除額10万円)で24.5万円、特例贈与は税率20%(控除額30万円)で62万円となります。最終的な納税額はこれらを合計した86.5万円です。
贈与において生前贈与になる場合とならない場合
生前贈与になり贈与税がかかる場合
生前贈与に該当し贈与税がかかるケースには以下のようなものがあります:
- 子の借金を親が代わりに返済した場合:この場合、実質的に資産を贈与したとみなされ、贈与税が課される可能性があります。
- 子が免除してもらった場合:借金の免除も贈与に該当し、贈与税が課税されることがあります。
- 親名義の自宅を無償で子の名義に変更した場合:これは明確な贈与として扱われ、贈与税が発生します。
- 満期保険金を保険料の支払いをしていなかった人物が受け取った場合:保険料を負担していない場合でも、受け取った満期保険金は贈与とみなされ、贈与税が課されることがあります。
このように、単なる資産の移転でなくとも、贈与と見なされることがあるため、注意が必要です。
生前贈与にならず贈与税がかからない場合
- 活費や教育費を扶養義務者から受け取った場合:通常必要と認められる範囲であれば、贈与税はかかりません。
- 個人から香典・見舞金・贈答・お年玉などを受け取った場合:これらの金銭も贈与税の対象にはなりません。
- 法人から贈与を受け取った場合:法人からの贈与は、基本的に贈与税の対象外です。
金銭の受け渡しが贈与税の対象となるか否かは、実際の事情や状況に応じて判断されるため、確認が必要です。
贈与税を非課税または節税できる制度
贈与税を節税または非課税で贈与を行うための制度には以下のようなものがあります
教育資金の一括贈与
「教育資金の一括贈与」制度では、平成25年4月1日から令和3年3月31日までの期間中に、子や孫ひとりあたり最大1,500万円の教育費を贈与する場合に、非課税となります。この制度を利用する際は、以下の条件を満たす必要があります。
- 贈与を受ける子供の年齢が30歳未満であること。
- 送金は金融機関を通じて行うこと。
- 習い事や塾といった学校以外の教育資金は500万円までが非課税の対象となる。
ただし、この特例措置は令和3年3月31日までに終了しているため、これから教育資金を贈与する場合には注意が必要です。
結婚・子育て資金の一括贈与
両親や祖父母から結婚や子育てのために金銭的な援助を受ける際には、「結婚・子育て資金の一括贈与」が適用され、非課税となります。条件は以下の通りです:
- 平成27年4月1日から令和3年3月31日の期間中であること。
- 結婚資金は300万円、子育て資金は1人あたり1,000万円までが非課税となります。
- 贈与を受ける人の年齢が20歳以上50歳未満で、前年の年収額が1,000万円以下であること。
- 送金は税務署ではなく金融機関を通して行うこと。
この制度も令和3年3月31日で終了しているため、新たに贈与を行う場合には適用されません。
住宅取得等資金の贈与
新たに住宅を購入する場合に、親や祖父母から資金援助を受けた場合には、「住宅取得等資金の贈与」が適用される可能性があります。条件は以下の通りです:
- 贈与が発生する年の1月1日時点で援助を受ける人が20歳以上であること。
- 平成21年分から平成26年分までの期間に「住宅取得等資金の贈与の非課税制度」を利用していないこと。
- 贈与を受けた人のその年の年間所得が2,000万円以下であること。
この制度を利用する際は、以前に非課税の適用を受けたことがある人は対象外となるため、注意が必要です。
夫婦間での居住用不動産の贈与
夫婦間であっても、一定以上の金銭の贈与があった場合には贈与税の対象となります。しかし、住宅の購入資金の取得を目的とした場合には、「夫婦間での居住用不動産の贈与」が適用され、非課税となることがあります。条件は以下の通りです:
- 結婚後20年以上が経過していること。
- 居住用の不動産を購入する資金であること。
- 贈与を受けた人が取得した住宅に翌年の3月15日までに居住し、今後も住み続ける予定があること。
結婚してから20年未満であったり、賃貸などの資産運用を目的とする場合には、適用されないので注意が必要です。
贈与税の3つの注意点
贈与税に関しては、以下の3つの注意点があります。
相続開始前3年以内の贈与は相続税の対象
生前贈与を行う場合には、贈与税の対象として年間あたりの贈与額を調整することで節税が可能ですが、相続開始前の3年以内に贈与を受けていた場合には、贈与税ではなく相続税として扱われてしまいます。親や祖父母から財産を受け取る際は、贈与者が3年間以上生存していることが求められます。
名義預金と判断されれば相続税の対象
親が子供の銀行口座に入金して分割で贈与を行った場合、税務署から名義預金と判断されるリスクがあります。名義預金と見なされると、子供の名義であっても実質的に親の財産と見なされ、分割贈与としては扱われません。親が亡くなった場合、子供の口座でも相続税の対象となりますので注意が必要です。
定期贈与とみなされれば贈与税の対象
相続税を逃れる目的で、親が子どもに毎年110万円以下の贈与をする場合、税務署から「定期贈与」とみなされるリスクがあります。この場合、帳簿上では贈与額が110万円以下であっても課税対象となることがありますので、注意が必要です。
まとめ
家族や親族間で1年間に一定金額を超える金銭や不動産などの財産の受け渡しがあった場合、贈与税の申告が必要になります。特に、年間あたり110万円を超える金額の贈与を予定している場合は、事前に確認しておくことが重要です。
贈与税には非課税や税率の優遇制度が設けられているため、これらの制度を理解し、上手に活用することが節税につながります。名義預金や定期贈与を行うと、贈与税ではなく相続税の対象になる恐れがあるため、慎重に行動することが求められます。また、令和3年時点で3,600万円以下の遺産を相続する場合、相続税は課されないため、生前贈与よりも遺産を相続するほうが節税に繋がるケースも考えられます。
理想の税理士を探すなら「税理士紹介をぶっ壊す」
- 税理士紹介サイトに騙されたくない
- 顧問料に応じた税務サービスを受けたい
- 税理士の人となりを自分の目で見て選びたい
「税理士紹介をぶっ壊す」では、このようなご要望をお持ちの方のための税理士検索サービスを提供しております。
税理士紹介サイトの「闇」を知らずに税理士を探される方もいるでしょう。
当サービスでは、本当の意味で、あなたにとって理想の税理士に出会うことが可能です。無料で今すぐ検索できるので、お気軽にご利用ください。